
こんな悩みを解決
- うまく教えられない
- 話すのが苦手
- 新人が分からないとイライラしてしまう
- 新人が分からないと落ち込んでしまう
- 良い指導が何のか分からない
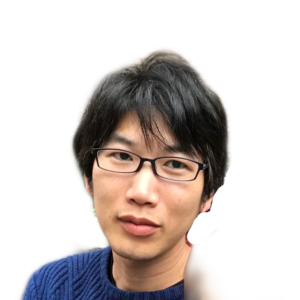
「新人指導って難しいなぁ」と思います。
しかし、指導者がするべきことは決まっています。
職種や内容によって教え方には違いがあるので、指導する側のマインドに焦点を当てて、良い指導者になるための記事を作成しました。
(具体的な指導方針や言葉や表現などの言い回しに関しては除外しています。)
この記事を最後まで読んでいただければ、教えることが楽しくなりますよ。
もくじ
(※便宜上、教える人を『指導者』・教わる人を『新人』と呼んでいます)
良い指導者になるマインド(1)心構え
指導を始める前に、指導の心構えを3つご紹介いたします。
寛容な心
厳しくせずに、ある程度のことは受け止める心が必要です。
新人がちょっと分からないくらいで指導者がいちいち不機嫌になっているようではいけませんよね。
誰にでも新人の時代があったはず。
指導をする際は、新人を暖かい目で見守る気持ちを心に留めておきましょう。
思いやり
人間の本質は『善』です。
こう言ったのは中国の思想家・孟子です。
人間は本来、善の生き物であるという『性善説』を説いた人物です。
過ちを犯すのが人間ではありますが、どんな人間も生まれながらにして善の心を持っているんだと思って、新人を思いやる指導してみましょう。
ミスを前提とした指導よりも、善意に訴えかけるような指導を心がければ、きっとうまくいきますよ。
指導の目的
指導の目的は、出来ないことが出来るようになることです。
つまり、あなたの役目は、新人が出来るようになるための案内です。
立場は違えど、指導者と新人・両者の目的は同じです。
目的達成のための協力者であることを前提として指導に当たりましょう。
心構えのポイント
新人を暖かく見守る寛容さ
善意に訴えかけるような指導
指導者と新人は目的達成のための協力関係
良い指導者になるマインド(2)論理的指導
思ったことをそのまま伝えていては、説明の順番がバラバラになりがちです。
まず最初に作業の全体像を提示するとスムーズに教えることができます。
「最初に全体を見せる』という教え方には2つの効果があります。
・現在位置が把握しやすい
・質問・相談しやすい
「何が分からないのかが分からない」という声を聞くことがあります。
こんなとき、指導者は新人の相談に乗ってあげることができません。
そうならないためにも、まず最初に全体像を提示することをお勧めします。
論理的な説明
論理とは、考えや法則を説明するための筋道を立てることです。
全体像を提示したあと、結論(目標・ゴール)を明らかにして、そうなるために必要な工程を順に説明していきます。
簡潔にした論理的な説明がこちら↓
論理的な説明の例
〈1〉『結論』を明らかにする
〈2〉結論に到達するために必要な『工程』『手順』を説明する
〈3〉『基礎』を教える
〈4〉過去の事例や自身の経験から、こうするとミスや間違いを犯しやすいことを『補足』する
〈5〉補足から得られることを『熟考』する
『全体→工程、工程→手順、手順→基礎』というように、マクロから徐々にミクロへ視点を移し、『補足』と『熟考』で学んだことを整理します。
いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのようにして——5W1Hをはっきりさせることで物事を整理しやすくなります。
そうすると、新人は「なるほど」「分かりやすい」と感じやすくなります。
あらかじめ、教育のプランを作成するのもアリです。
論理的教育のポイント
マクロからミクロへ順に説明する
5W1Hをはっきりさせる
良い指導者になるマインド(3)自己レベルを上げる
指導者は、新人にとって、仕事仲間としての基準になる人です。
新人は指導者をこう見ている
・この人は頭いいな
・この人は優しいな
・この人は言葉遣いが柔らかいな
・この人は人間ができているな
・この人の経験則はすごいな
・この人は頼りになるな
etc
新人といえど、指導者のレベルを見抜いてきます。
話す言葉や態度が上辺だけにならないように、日頃から自分のレベルを底上げしておきましょう。
レベルUPのポイント
自己のレベルが上がれば自然と良い指導ができる
日々、修練
良い指導者になるマインド(4)意欲を持続させる
指導者が新人の意欲を失わせるようなことは絶対にあってはなりません。
仮に、理解が遅くても、勘違いしていても、ミスを連発していても、意欲があればなんとかなります。
人によって学習のスピードは違います。
学習のスピードが速いからといって、作業も速いかといったら、それはまた別問題です。
新人の意欲を損なわないように気をつけましょう。
意欲を失ってしまったら
もしも意欲を失ってしまったら、何らかの要因があると思って考えてみましょう。
意欲を失った要因は……
・一部、苦手な作業がある
・肉体的にキツい
・労働環境が不満がある
・給料が安い
・人間関係がうまくいってない
・作業が楽しくない
・実際にやってみて興味が無くなった
etc
すべてを解決することは無理ですが、そういうときは励ましたり、相談に乗ってあげましょう。
「なぜ、そこまで面倒見なきゃいけないんだ」と思うかもですが、それが指導の任務です。
「これが面白いんだよ」「これが楽しいんだよ」と、その作業の魅力を伝えるような指導に努めましょう。
意欲持続のポイント
新人の意欲を損なってはならない
新人の意欲を持続させるのも大切な務め
良い指導者になるマインド(5)指導の楽しさを知る
指導はよく育児に例えられます。
ですが、本当の自分の子ではないので、なかなかそうは思えないものです。
ひとまず、自分の子が大人に成長する様子を想像してみましょう。
あなたの子は将来、親が望んでいるような大人になるのか……。
おそらく、そうはならないでしょう。
わがままで自分勝手で、小さくて弱くて、失敗や間違いを繰り返しながら、それでも前に進もうとする——それが人間。
知識が乏しく、弱いくせに、怖いもの知らずで危なっかしい。
……だからこそ、親は子を可愛いと思うのでしょうね。
それと同じように、新人も指導者が望むような人間にはならないでしょう。
だからこそ、たとえ他人であっても可愛いのかもしれません。
間違った方向へ進もうとしてるのを放っておけず、軌道修正してやらねばならない、と思える存在なのでしょうね。
大変だから良い
指導がうまくいかないときは、それを良いものとして考えてみてください
たとえば、指導には時間と労力が伴います。
新人の上達が遅くてイライラしたこともあったかもしれませんね。
新人のためのを思って時に厳しい言葉を発してしまったこともあったかもしれませんね。
「怒りたくないのに……」と自分を責めてしまったこともあるかもしれませんね。
新人が一人前になるのは大変です。
ですが、その甲斐あって、新人が一人前になったとき、あなたの指導はとても価値があったと思えるのではないでしょうか。
指導は〇〇
ここに、一人前になろうと頑張っている人がいます。
その人を助けられるのは指導者のあなただけです。
助けてあげたいと思いませんか?
どうですか。
助けてあげたいと思ったなら、そこにやり甲斐や使命のようなものを感じたのではないでしょうか。
だから、指導は楽しいのです。
意欲持続のポイント
新人が一人前になることは大変だが、それが楽しい
指導は大変だが、それが楽しい
新人にうまく教える良い指導者になるためのマインド まとめ
これまでのポイントをおさらいしておきましょう。
・マインド(1)心構え
→新人を暖かく見守る寛容さ
→善意に訴えかけるような指導
→指導者と新人は目的達成のための協力者
・マインド(2)論理的指導
→マクロからミクロへ順に説明する
→5W1Hをはっきりさせる
・マインド(3)自己のレベルを上げる
→自己のレベルが上がれば自然と良い指導ができる
→日々、修練
・マインド(4)意欲を持続させる
→新人の意欲を損なってはならない
→新人の意欲を持続させるのも大切な務め
・マインド(5)指導の楽しさを知る
→新人が一人前になることは大変だが、それが楽しい
指導は大変だが、それが楽しい
指導していると、いろんなことで悩んだり葛藤します。
でも、新人にしても、一人前になろうとして悩み葛藤しているのです。
だからお互い、時間をかけてその苦労を乗り越えたときに、最高の成果を作り出すことが出来るのだと思います。
今のままの気持ちで指導に精を出してください。
この記事であなたの悩みが解消されたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。^ ^
【関連記事】
-

-
【解説】ルソー『エミール』(講談社まんが学術文庫)|結論|感想|読み方
まさに 理想の子育て 家庭教師の〈レオ〉はとある事情で息子を1人で育てることに……。〈ルソー〉の教育論に則って教育された〈エミール〉は、自然 ...
続きを見る
ブログ記事を有益と思っていただけたら また見に来ていただけると嬉しいです
フォロー ブックマークをしていただけると ブログ更新を見逃しませんよ(^^)