
まさに
理想の子育て
家庭教師の〈レオ〉はとある事情で息子を1人で育てることに……。〈ルソー〉の教育論に則って教育された〈エミール〉は、自然の中でのびのびと成長していく——。
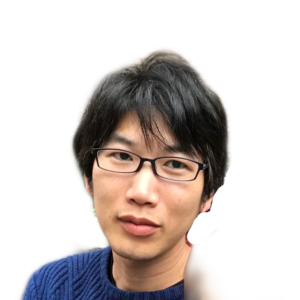
今回は【講談社まんが学術文庫】の中から『エミール』を簡単5分でご紹介します。
結論
この本が教えてくれるのは、社会と共存できる自由な人間の育て方です。
感想
『エミール』との出会い
恥ずかしながら何の予備知識もありませんでした。
『エミール』は女性の名前で、恋愛小説か演劇かと思っていました。
簡単あらすじ

1776年 フランス パリ
〈レオ(27)〉は貴族の子〈エギヨン(7)〉の家庭教師をしていました。
エギヨンはわがままで傲慢な性格でしたが、雇われの身のレオは教育方針を変えることはできませんでした。
この時代、街全体が狂った人間が作り出した欲望の産物で溢れかえっているかのようです。
帰宅したレオが一息をついていると、外から「フンギャーッ!」という鳴き声が聞こえてきました。

なんと家の前に赤ん坊が捨てられています。しかも置き手紙があり、そこには”あなたの子です。私は決められた婚約者と共に人生を歩みます。この子はあなたに委ねます。 マルシアより”と書かれていました。
「マジかよ!!」
レオも捨てられた孤児だったが、貴族夫人に救われ、貴族の子どもたちの家庭教師として、規則に沿った教育を施してきた。しかし、それは間違っていた。人の本来の自由を奪うものだった。
レオは男の赤ん坊を〈エミール〉と名づけ、実父〈ルソー〉の教育論を実証することを決意する。
自然人教育

——6年後
エミールは自然の中でたくましい少年に成長していた。
今していることは先天的な感覚の発達を育む”自然人教育”。それは自然に任せて余計な指導はせず、距離を取りながら”3つの先生”によって成長を見守る消極教育である。
3つの先生とは
1. 弱い存在として生まれる我々には力が必要だ。それには自然の教育が求められる。
2. 何も持たずに生まれる我々には助けが必要だ。よって人間の教育が求められる。
3. 何の分別も知らず生まれる我々には事物の教育が求められる。
この3種類の先生によって、人は一貫性のある人生を歩めるようになる。

教育方針を大きく分けると
0〜15歳までを”自然人教育期” (自然人=自分のために生きる人間に導く)
15歳以降を”社会人教育期” (社会人=思いやりや共感力のある人間について教え学んでもらう)
発達段階を詳細に示すと
0歳〜1歳 乳幼児期 快・不快を育む
1歳〜12歳 児童・少年期 感覚・知覚を育む
12歳〜15歳 少年後期 好奇心・有用性を育む
15歳〜20歳 思春期・青年期 理性・道徳を「教わり学ぶ」
20歳以降 青年期後期 人間の幸福と徳について「学ぶ」

大自然に放ったらかして育てる。端から見て手抜き教育に見えますが、大人には仕事があり、ほったらかしにもそれなりの覚悟がいります。この理論を発案したルソーは「現実的に完璧な実践は困難。あくまでも理想」と唱えている。
自然の中で活動する
↓
好奇心を持たせ、自由に運動する
↓
様々な体験から五感を発達させる
↓
有用性を感じる物事から学びを始める

自然の中での体験により、体力・感覚・理性・判断力を発達させる事が最重要!!
(現代教育の学問と一般教養は幼児期・少年期に本来必要な成長過程を台無しにする。)
積極的教育

「父ちゃん。オレ、あいつらと遊んだ方がいいのか?」エミールは麓で遊んでいる子どもたちが気になるようです。
「おまえはどうしたい?」とレオが問い返すと、エミールは「オレは森の探検で忙しいからな……森に行く」と答えた。
レオはエミールが次の段階に入ったと感じた。
幼児期から少年期にかけて、同世代に必ずガキ大将が現れる。大抵は腕力で人の物を独占し悪の観念による影響を与える。だが、悪を知る前に正義の観念を先に知っておく方が分別のある人間になる。そこで積極的教育だ。
ある日、エミールが「ソラマメを食べたい」と言ったが、食べたので無い。じゃあ、どうすれば食べられる?——ということで、レオは自分で栽培することを勧めることにした。
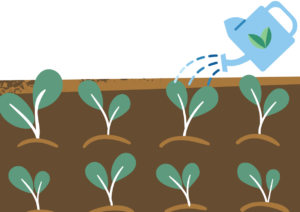
その日からエミールは毎日、水やり、手入れを欠かさず行った。
月日が経ち、待ちに待った収穫の時期。しかし、翌日……ソラマメの畑は無残に荒らさていた。エミールは大泣きした。
犯人は庭師の〈ロベール〉だった。
実は、この畑はロベールの土地で、そもそも、先にメロンを植えられていたのだ。酷い事をしたのはエミールの方だった。
レオはロベールに謝罪し、エミールに正義と悪の観念を教えようとしたが……「イヤだぁぁぁぁっ。ソラマメを返せぇっ!!」と叫んで遠くへ走って行ってしまった。
こんな時に限って大雨が降る等のハプニングもあったが、この世界が自分だけのものではなく、所有者がいるものを勝手に奪ってはいけない、もし間違ってしまったら素直に謝り話し合って仲直りする”正義の観念”をを教えることができた。
社会人教育
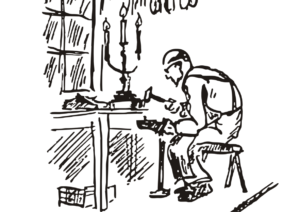
8年後 1790年
レオは自然人教育の仕上げ、社会人教育の旅の準備段階に入る。
来週からエミールは週に2回、街の家具職人の下で徒弟として働くことになった。
社会人教育の旅の準備
職人の徒弟や工場でインターンシップを行いながら学ぶ
社会は1人では成り立たない
↓
社会は「分業と交換」で成り立つ事を学ばせる
職業見学(業種を知る)
↓
インターンシップ(仕事の経験)
↓
工場見学(分業を知る)

エミールはレオに言います。「父ちゃん、世界って広そうだな……。オレ、旅に出てもっと知りたいよ」
レオはこう言います。「ああ、その時が来たようだな。世界を見に行こうか」
社会と共存する心を育む

エミールは教育の場を自然から社会へと変え、社会の仕組みと人を思いやる心を学んでいきます。
●他者を憐れむ心[友愛]
●特定の人を慈しみ思いやる心[情愛]
●他者を愛し、他者の幸福を願う心[博愛]
エミールは時に失敗し、時に回り道もしますが、レオの目標とする社会と共存し他者を思いやる人間に成長していきます。
読み方
ジャン・ジャック・ルソーの教育論を手本とした子育て物語です。
子どもを育てる時、自分勝手で傲慢で他人を馬鹿にして喜ぶような大人になってほしいと願う人はどこにもいないでしょう。
人の育成はあくまでもその人個人によるものだと思いますが、いい環境・いい指導を与えることが大事なことを本書では教えてくれます。
「なんでこんな子に育ってしまったの!」と思った事のある人が『エミール』を読めば、今すぐにでも良い教育者に変われると思います。
なぜなら、人間誰しも心の中では、自由で純粋で他者を思いやる人間になりたい(なってほしい)と望んでいるからです。
最後に
まずは漫画で読むことをオススメしていますが、書籍で読むのもいいと思います。
書籍は、図書館や中古本など、たくさんあると思います。
ぜひ探してみてください。^ ^