
まさに
現代版・仕事戦術
リーダーシップ、マネジメント、モチベーション、マーケティング、問題解決力……働く人には課題が山積み。そんなあなたに『孫子の兵法』があらゆるビジネスシーンを成功へ導きます——!
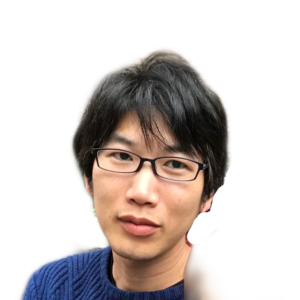
僕が大好きな本 『決定版 孫子の兵法がマンガで3時間でマスターできる本』を簡単10分でご紹介します。
結論
この本が教えてくれるのは、仕事がうまくいく秘訣です。
感想
『決定版 孫子の兵法がマンガで3時間でマスターできる本』との出会い
仕事の悩みは尽きません。
『孫子の兵法』はビジネス本としても活用できると言いますが……。
第1章 人を導く「リーダーシップ」

001 指示は一度に一つまで
告ぐるに言をもってするなかれ
◆「小言」で部下は動かない
「Aくん、この書類には誤字があるよ」
「机の上に物を置きすぎじゃないか?」
「ネクタイが曲がってるぞ」
「朝の挨拶の声が小さいねぇ」
このように、部下に対してあれこれ注意する人がいる。社会人としての常識やマナーを身につけさせるために、適切な指導をすることは大切だ。
だがそれが、単なる”小言”になってしまっては意味がない。ダラダラ小言を言われた方は「ハイハイ、分かってますよ」などと、心の中で反発してしまうだけだ。
(省略)
◆指示も注意も一つの事柄にフォーカスする
孫子は「告ぐるに言をもってすることなかれ」と言っている。「指示に余計な言葉や文章は不要である」と説く。言い換えれば、指示をするときも、注意を与えるときも、一つのことに絞るべしということである。
書類の不備を修正させたいのなら「この書類の誤字を修正しなさい」とだけ伝える。たとえ他のことが気になっても、まずは書類の誤字だけ直させるのである。
(省略)
指示をするときは一つの事柄に焦点を絞ろう。一度にたくさんのことを伝えても、部下は動かない。
右が文章 左がマンガ
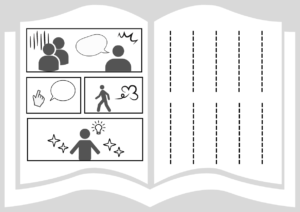
1つの課題に対して、2ページ構成になっています。(1ページ目が文章、2ページ目がマンガです。)
・1ページ目の前半では、実例にそった解説がなされます。
例えば、〇〇の会社が、もしくは会社員・経営者が〜〜をして○△×□になった。後半では、そこで『孫子の兵法』にはこんな言葉があるように、こういう時は◎◎な思考・行動が成功するために必要だと教えてくれます。
・2ページ目は1ページの内容をマンガでまとめています。
マンガだけを読んでも内容はわかるようになっているので安心して読めます。
目次

全部で13章、100の課題と知恵が載っています。
●第1章|人を導く「リーダーシップ」
001 指示は一度に一つまで(告ぐるに言をもってするなかれ)
002 よく考えてから命じる(よく兵を用うる者は、役再び籍せず)
003 ツボを押さえて話す(諄々翕々として徐に人と言うは衆を失えるなり)
004 柔軟性を持つ(廉潔は辱むべきなり)
005 信頼して任せる(将、能ありて君の御せざる者は勝つ)
006 困難な課題に挑戦させる(害に陥りてしかる後よく勝敗を為す)
007 情に流されない(民を愛するは煩わすべきなり)
008 行動指針を示す(能く士卒の耳目を愚にし、之をして知るなからしめよ)
●第2章|組織を管理する「マネジメント」
009 指揮系統を理解する(三軍の権を知らず)
010 部下の扱い方を知る(服せざれば即ち用い難きなり)
011 できない社員を活かす(敵の一鐘を食するは吾が二十鐘にあたり)
012 現場に指揮権を与える(主、戦うなかれというも、必ず戦いて可なり)
013 破格の褒章を与える(無法の賞を施し、無政の令を懸く)
014 社員の健康に配慮する(生を養いて実に処れば軍に百疾なし)
015 適切な距離感を保つ(卒を視ること愛子の如し)
016 部下を気に掛ける(卒を視ること嬰児のごとし)
017 マナーを身につけさせる(士卒いずれか練いたる)
●第3章|やる気を引き出す「モチベーション」
018 自信を持たせる(疑を去らば死に至るまでゆく所無し)
019 「期待している」と伝える(よく兵を用うる者は、譬えば卒然のごとし)
020 相手に合わせて対応する(敵の変化によりて勝を取る者、これを神という)
021 小さなゴールを設定する(兵は勝つを貴び久しきを貴ばず)
022 一人ひとりに声をかける(道とは、民をして上と意を同じくし)
023 相手に逃げ道を残す(囲む師は必ず聞く、窮寇には迫ることなかれ)
024 音楽やリズムを取り入れる(その人を戦わしむるや木石を転ずるがごとし)
●第4章|市場と顧客を攻略する「マーケティング」
025 一つの分野に特化する(国を全うするを上と為し、国を破るはこれに次ぐ)
026 見込みだけで勝敗を判断しない(いわんや算なきにおいてをや)
027 相手の耳に届く言葉で語る(言えども相聞こえず、故に金鼓をつくる)
028 提案内容を活かす(厚うしてよく使わず)
029 本音と建前を探る(辞卑しくして備を益するは進むなり)
030 自分の力と相手の力を熟知する(彼を知り己を知れば百戦して危うからず)
●第5章|課題を乗り越える「問題解決力」
031 事実に注目する(之を犯うるに事をもってす)
032 準備をしてから追い込む(之を住く所なきに投ずれば、死すとも且つ逃げず)
033 欠点の裏に利点がある(客たるのは道は深ければ即ち専らに、浅ければ即ち散ず)
034 クレーム処置は午後に行う(朝の気は鋭く、昼の木は惰す)
035 問題への対応は迅速に(兵は拙速を聞くも、未だ功の久しきをみざるなり)
●第6章|意識を高める「マインドセット」
036 「できます!」と声に出す(勝は知る可く為す可からず)
037 仕事を止めない(衆を治むること宴を治むるがごときは、分数是なり)
038 コスト意識を持つ(日に千金を費やし、然る後十万の師挙がる)
039 マイナスをプラスに変える(迅をもって直と為し、憂いをもって利と為す)
040 甘い見通しをしない(その来たらざるをたのむことなし)
041 レイアウトを工夫する(それ地形は兵の助なり)
042 置かれた場所で咲いてみる(兵に常勢なく、水に常形なし)
●第7章|負けないチームをつくる
043 「どうすればできるようになるか」考える(兵には走る者あり)
044 ゴールをイメージする(弛む者あり)
045 部下の適正や可能性を見極める(陥る者あり)
046 いくつかのグループに分ける(崩るる者あり)
047 指示の内容を明確にする(乱るる者あり)
048 負けるべくして負けない(北ぐる者あり)
●第8章|人を動かす「説得術」
049 相手の言い分を受け入れる(兵を為すことは敵の意に順詳するにあり)
050 ヒアリングに力を入れる(諸侯の謀をしらざる者は、予め交わる能わず)
051 基準や尺度の違いを知る(声は五に過ぎざるも五声の変は勝げて聴く可からず)
052 基本的なことから伝える(此れ兵家の勝にして、先に伝うべからず)
053 相手が知りたいことだけ話す(告ぐるに害をもってすることなかれ)
054 状況に応じたツールを使う(兵を知る者は動きて迷わず)
055 環境を味方につける(一に曰く「度」)
056 相手のメリットを提示する(敵をして自ら至らしむるは、これを利すればなり)
●第9章|事態を好転させる「交渉術」
057 決断を引き出す(将は国の輔けなり、輔、周ければ即ち国必ず強し)
058 大切な話は一つだけ(力を一に併せて敵に向かえば、千里に将を殺す)
059 相手の本音を探る(半ば退くは誘うなり)
060 数の多さに頼るな(兵は益々多きを尊ぶにあらざるなり)
061 正攻法と奇策を使い分ける(正をもって合し、奇をもって勝つ)
062 席の配慮を工夫する(此れ兵の利、地の助なり)
063 相手に決めさせる(勇を斉しくして一のごとくならしむるは、政の道なり)
064 相手の真意を探る(辞強くして進駆するは退くなり)
●第10章|有利に戦うための「ビジネス戦略」
065 安全には万全を期す(その攻めざるをたのむなし)
066 戦うべきでない時を見極める(以て戦うべきと以て戦うべからざるとを知るものは勝つ)
067 他者がしていないことをする(千里行けども労せざるは、人無き地を行けばなり)
068 戦いの後にも配慮する(明主は之を慮り、良将は之を修む)
069 最良の形は変わる(兵に形すの極みは、無形に至る)
070 時には演技をしてみる(善く戦う者の勝つや、智名も無く勇功も無し)
071 マネできないほど極める(微なるかな微なるかな、形無きに至る)
072 勝てる見通しをつけてから戦う(勝兵はまず勝ちてしかる後、戦を求む)
073 戦わずに勝つ方法を見つける(戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり)
074 ブルーオーシャンで勝負する(進みて防ぐべからざるはその虚をつけばなり)
●第11章|仕事を前に進める「情報収集・活用」
075 情報の意味を読み取る(塵高くして鋭きものは、車の来るなり)
076 生きた情報を収集する(郷間あり、内間あり)
077 内外に情報源をつくる(三軍の事、間より親しきは莫し)
078 リアルタイムの現地情報を得る(郷導を用いざる者は地の利を得るあたわず)
079 多種多様な情報に触れる(鳥集まるは虚なるなり)
080 調査データは客観的に見る(兵多しといえどもなんぞ勝に益あらんや)
●第12章|自己成長を促す「習慣」
081 見かけで差をつける(兵は詭道なり)
082 威厳を演出する(威、敵に加われば、即ちその交わり合うを得ず)
083 「マネ」を活用する(形によりて勝ちを衆におく)
084 第一印象で良いイメージを与える(これに形すれば敵必ずこれに従う)
085 先手を打ち、主導権を握る(善く戦う者は人を致して人に致されず)
086 相手ではなく自分を変える(敵をして必ず勝つ可からしむ能わず)
087 スキマ時間で自分を磨く(吾がもって待有るを恃むなり)
088 時間前に現地入りする(先に戦地に処りて敵を待つ者はいつし)
089 どんなときでも遅刻しない(遅れて戦地に処りて戦に赴く者は労す)
090 怒りにまかせて行動しない(憤りをもって戦いを致すべからず)
●第13章|厳しい社会を生き抜くための「心構え」
091 批判にも耳を傾ける(智者の慮は必ず利害を雑う)
092 過去の成功に安住しない(秋毫を挙ぐるは多力となさず)
093 守りを固める(善く守る者は九地の下にかくる)
094 敵味方の双方と駆け引きをする(用あればこれに用あらざるを示す)
095 冷静に合理的な判断をする(これをもってこれを観れば勝負あらわる)
096 得意分野で勝負する(よく自ら保ちて勝ちを全うするなり)
097 出し惜しみしない(積水を千仞の谷に決するがごときは形なり)
098 追い打ちをかけない(帰る師はとどむることなかれ)
099 ここ一番で「赤」を用いる(人の兵を屈するも戦うにあらざるなり)
100 混乱の中に秩序を見出す(紛々紜々として戦い乱すべからざるなり)
目次だけでも物凄いボリュームです。(全248ページ)
読み方
実例にそって『孫子の兵法』の知恵をマンガで分かりやすく説明してくれる内容です。
手っ取り早く知りたい時はマンガだけ読んで、深く知りたい時は文章も読む。そんな読み方でいいと思います。
文章から読むかマンガから読むか、どっちから読んでも差し支えなく、自由な読み方ができるのが嬉しく、初心者にも優しい点です。また、「3章だけ読もう」というふうに、読みたい所だけサクッと読めるもこの本の面白みです。
長く売れ続けているのも納得です。
最後に
『孫子の兵法』の中で社会人として役立つ本はこの本です。
どんな困難にも負けない人になりましょう!

まずはレビューをご覧ください
-
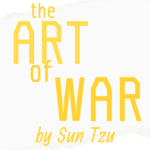
-
【解説】遠越段『図解 大人のための孫子の兵法』|結論|感想|読み方
まさに 書き下し文、その意味 孫子の兵法のエッセンスは現代でも色あせない。 過酷な時代を生き残る術を孫子の名言から学ぶ——。 よーいち敵を打 ...
続きを見る