
まさに
中華大乱
紀元2世紀 漢王朝は衰退。 いつからか黄巾賊という武力集団が出現し、各地で略奪・暴虐の限りを尽くしていた。 国の将来を憂う青年〈劉備〉は〈関羽〉〈張飛〉2人の豪傑と出会い、指導者として決起する——!
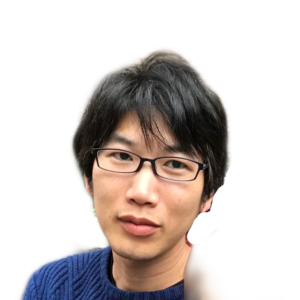
■結論
この本が教えてくれるのは、人の生きざまです。
■あらすじ

黄巾の乱
紀元2世紀 中国はすでに悠久たる太古より連なる二千年の歴史を有する大国であった。
しかし……約四百年もの長きにわたって中国に君臨した漢王朝は宦官の専制による政治腐敗が極限に達し、人々は重税にあえぎ、連日の日照りと凶作が重なって、飢えと苦しみのどん底にあった……!
宦官(かんがん)とは、去勢を施された官吏である。古代から各文化圏に存在した。
Wikipediaより引用
せん-せい 【専制】
1 上に立つ人が独断で思うままに事を処理すること。
コトバンクより引用
中平元年(184)
漢王朝打倒を旗印に各地の飢民・流民を組織化して決起した黄巾賊の反乱はいつしか略奪強盗の暴徒と化し、人々を恐怖のどん底におとしいれていた……!
国は乱れ、いま、まさに断末魔の時を迎えようとしていたのである!
涿県 楼桑村
黄巾賊の容赦の無い襲撃を受けて、家屋は荒らされ、食料や女は奪われ、男は殺された。
「ま、待って下さい!」と、1人の男が駆け寄って行った。「食糧は大方税に取られ、残っているのはわずか。それすら奪われては村の人たちは餓え死にしてしまいます! どうかお返しを!」
この勇敢な男の名は〈劉備〉。草鞋売りの青年だった。
黄巾賊の男は「よし、わかった!」と言って手土産に劉備の首を要求した。命を惜しさにひるむであろう脅しではあったが、「どうぞ……わたしの首でよければ」と、劉備は歩み寄っていく。
——と、そこに〈張飛〉と名乗る骨太な男が現れ、黄巾賊の奴らをものすごい勢いで薙ぎ倒していった。
事無きを得た劉備は張飛を家に招くと、劉備の母は「息子の命の恩人でございます」と言って大いに食事を振舞った。張飛は食事のお礼にと薪割りを済ますとさっさと帰って行った。
その晩、劉備は村を出ていく母子を目にする。
彼らの父と兄は黄巾族に殺され、隣村の義兄のところで面倒を見てもらうしか他に生きていく方法がないと寂しげに去って行った。
劉備は自分の無力さを嘆いた。「私にあの張飛という男のような剛力さえあったら!」
■立て札
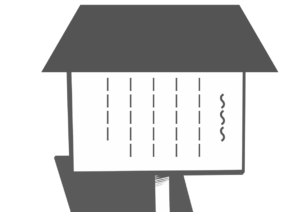
ある日、村にある立て札が出された。
黄巾賊を討伐するために義兵を募集する、という内容だった。
義兵(ぎへい)とは、正義のためにおこす兵のこと。
Wikipediaより引用
黄巾賊の大将〈張角〉という男は恐ろしい呪術を使うと言う。
張角は故郷・鉅鹿郡では希代の秀才といわれていたが、官吏試験に失敗し、隠遁生活を送っていた。ある日。山で薬草を採取していたところ、仙人に出会い、太平要術を授かった。そして数年後、風雨を呼び起こす力を体得。国中に疫病が流行した際、その力をもって人々を救った。その評判は全国に知られるところとなり、ありとあらゆる人々が集まるってくるようになっていた……。彼らは黄色い布で髪をしばって仲間のしるしとして組織化し、平和な世の中の実現を目指して武装蜂起したのである。
しかし、その集団はいつしか略奪殺戮を繰り返す鬼賊と化していったのである! その数、40万以上。
劉備は「わたしに力さえあれば……」と尻込みしていたが、そこに張飛がやって来た。
張飛が「てめえ、黄巾賊にあれだけやられてくやしくねーのか!」と劉備に喝を入れていると、「カッハッハッハ!」と高らかに笑う〈関羽〉という顎鬚の男がやって来た。関羽は張飛の兄貴分で、弟分の無礼を詫びると去って行った。
■漢王朝の血

関羽が張飛と酒を飲み交わしていると、さきほどの男が劉備という人徳者である事を知る。
「劉備こそ、オレが探し求めていた男に間違いない!」
関羽はすぐさま張飛に劉備の家を案内させた。そして、劉備の家に着くと、劉備の持っている、人を魅きつける力こそが指導者たる者の資質だと力説した。
「玄徳!(劉備のあざな) どうやら、おまえが立つときがきたようですね」
話を聞いていた劉備の母は1本の剣を持って来て言った。「この剣は先祖代々わが家に伝わる皇帝の末裔としての証の秘宝。おまえは漢の中山靖王〈劉勝〉の後胤(=子孫)、景帝の血を引く身の上! よもや忘れたわけではありますまい」
「な、なんだと!」関羽は驚き、劉備の前にひれ伏して言った。「この国の危機を救うため、われらが主君となってお立ち下され!」
「わたしには力がない……しかし……関羽! 張飛! あなたたちが助けてくれるというのなら、この劉備、国のために立たん!」
■桃園の誓い

「我ら三人、義兄弟の契りを結んで天に誓う! 生まれた日は違えども、死す時は同じ日同じ時を!」
志を一つにした劉備、関羽、張飛は桃園で義兄弟の契りを結び、酒を酌み交わした。
すると、村の男たちが「われらも劉備どのの義軍に入れて下さい!」と大勢集まってきた。こうして、多くの男たちが参集した。その夜は遅くまで村人と酒を飲み明かした。
——明朝、〈張世平〉という男がたくさんの馬を引き連れて来た。彼の故郷も黄巾賊に襲われ、財産と妻子の命を奪われた被害者だったのだ。馬を売りに行った際に劉備の噂を耳にして、軍馬として使ってもらいたい思いで来たと言うのだ。さらに武器などの資金としてのお金も工面してくれた。
こうして劉備は軍馬と武器と防具を揃え、いざ黄巾賊を討伐するべく進軍したのだった。
この時、劉備23歳。義軍総勢500余名。長く苦しい遠征の始まりであった……。
■そして大乱へ

黄巾賊との戦いを勝利でおさめた劉備だったが、この戦いは皮肉にも、董卓、曹操、公孫瓚、袁紹、袁術、孫堅、呂布などの群雄を生みます。
この後、力を持った武将たちが権力を我がものとせんとして、血を血で洗う討滅戦へと移り変わっていきます。そして、戦略が中心となった戦いが始まると、軍師の活躍が目立つようになり、ストーリーは盛り上がりを見せていきます。
国の情勢や地形や天候などを丹念に調べて戦略を練っている軍師のシーンは、とても為になりました。
いろんなキャラクターが良くも悪くも活き活きとしていて、読んでいてスカッと爽快な気分になれました。今の時代、我慢することが多いからかも知れません。
男の本能だと思いますが、それを思い出すことができました。
![]()
■ハイライト
・ストーリーが分かりやすい
・数十万規模の戦争
・リアルなキャラクターの描写
・かっこいい武具
・臨場感あふれる戦闘シーン
・男たちの生き様
・諸葛亮孔明の知略
■【余談】好きな武将の小話
僕が一番好きな武将は曹操です。
彼は、孫子の兵法に精通していて、いろんな戦略を駆使して戦う頭脳派で、尚且つパワフルな側面を持つ豪傑です。にもかかわらず、情報不足で軍を動かしたり、感情的な決断も多く、何かしらで孔明の策略に嵌められることもしばしばあります。
そこがなんとも言えず、愛おしさを感じてしまいます。
それに、曹操は身分や出身で人を区別せずに、能力のある者は率先して登用したといいます。曹操の器の大きさと柔軟な思考にも好感が持てます。
『三国志』のストーリーは、劉備と曹操が中心となって展開することが多いので、ぜひ注目してもらいたいと思います。